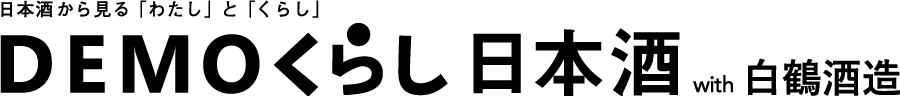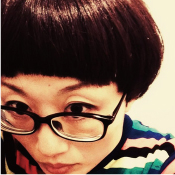文:いしづかたかこ
母方の祖父母の家で生まれ育ち、物心ついたとき、父とは一緒に暮らしていなかった。
時折やってきては、遊びに連れて行ってくれる父。
なぜいないのかとか、寂しいとか、考えるにはまだ幼すぎた。
ある日を境に父は来なくなった。今思えば、正式に離婚が決まったのだろう。
正座して祖父母に頭を下げる父の後ろ姿が幼心の記憶にある。
その日から祖父は祖父であり、私の父となった。
言わずもがな、小さなころから祖父にべったりだった。
どこにいくにも祖父のあとを追い、祖父の膝に座っていた。
父のいない寂しさを埋めるためだったのかもしれない。
「オレの言うことがすべてだ」
「大黒柱のオレに逆らうのか」
と横柄を言う祖父だが、幼き私には優しかった。
祖父はいつも煙草を吸っている。
親せきや仲間内と集まるときはプカプカふかしながらマージャンをする。
ただ、祝いの席だろうが、なんだろうが、酒は一滴も飲まない。
飲めないのだ。
酒を勧められると照れながら「いや、オレは飲まんよ。車あるからな」とはぐらかしていた。
私が「お酒っておいしいの?じいちゃんは飲まんの?」と聞くと
「酒は神さまの飲み物やからな。ご先祖様に飲んでもらうわ」
とさも誇らしげに答えた。
信仰心の厚い祖父は、毎朝欠かさず神棚に米と塩と水をお供えして、月に1度酒とともにご馳走をお供えしている。
けれど、うちは誰も飲まない。
お酒を飲むご先祖さまなんかいるのだろうか?
供えられた透き通った酒を見てはきっとおいしいものなのにもったいない。と思った。
台所には全く減っていない酒ビンがいつも並んでいた。
あんなに大好きだった祖父とは、中学生ごろからあまり話さなくなった。
いわゆる思春期というものだろう。
毎日言い争いも絶えない。
考え方も違ったし、祖父の信じるものも理解できなかった。
そして、私は家を出た。
少し落ち着いて話せるようになったのは、結婚して子どもを産むために戻ってきたときのこと。
あの勇ましい祖父の姿はどこか小さくなっていた。
祖父はいつものように神棚にお供えをしていた。
ひ孫を抱いてもらうこと以外、私は何も祖父にしてあげられていない。
最後までわがままを言う娘だった。
実家へ帰るとまず神棚と仏壇にあいさつする。
相変わらず、神棚の酒はおいしそうだ。
実は、ひそかにお下がりの酒をいただいている。
台所に並んでいるビンもいただいて帰る始末。
今、わたしにできるのは、酒を飲みながらオヤジたちに想いを馳せることだけ。
酒を飲みながら、子どもたちに思い出話を聞かせている。
私だけ酒のみなのは遺伝なのかもしれない。
じいちゃん、酒おいしいよ。
ほどほどにしなかんけどね。