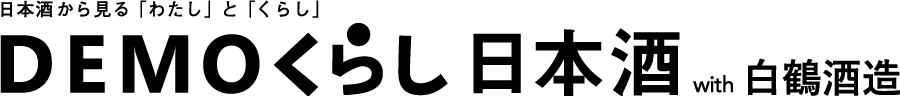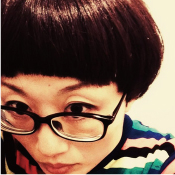文:小倉なおこ
「今週末は被災地に行くぞ。」
父が突然そう言い出したのは、震災から3週間ほどたったころだろうか。
1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災。震源に近い神戸市の被害は甚大で、テレビ画面を見ながら、何かものすごく大変なことが起こったのは、子どもながらにもひしひしと感じた。
「えっ、ニュースのあの場所に行くの?何するの?行けるもんなの?」
当時小学生だった私は、訳も分からぬまま車に乗り込み、岐阜から神戸へと向かった。
「カレーありますよー!どうぞー!」
私は父の知人の紹介で、カレーの炊き出しをしていたパキスタン人ボランティアグループのお手伝いをすることになった。パキスタンってどこ?スパイスカレーなんて、見たことも聞いたこともない。スープみたいにシャビシャビしたカレーだけど…ナニコレ!めちゃくちゃおいしい!
辺りを見渡すと、川沿いにつづく公園には、たくさんのテントが並んでいた。ほわほわ〜っと良いにおいが漂ってくる。うどん、おにぎり、おでんなど色んな炊き出しがつづく。奥へと進むとトイレットペーパーや毛布、ゴミ袋など生活用品が所狭しと並べられているエリアもあった。
「うどんいかがですかー!あったまりますよー!」
あちこちから、そんな声が聞こえてくる。確かその日の夜は、車中泊をしたと思う。お風呂だけは貸してもらえる事になり、お風呂が使えるお家にお邪魔した。家の中は薄暗かった。まだ地震の後の色んなものが片付いてなかった。そのお家には、入れ替わり立ち替わり色んな人がやってきて、お風呂に入っていった。
だんだんと頭の中が混乱してきた。
スパイスカレーの香り。無料で配られる毛布。うどん。家のお風呂に色んな人が入りに来るとか?なんなんだこのセカイ。
大人になった今なら、頭で理解できるけれど。当時の私には、その日見た「人々が助け合う光景」が衝撃的だった。こんなセカイがあるのか——
あの時、人々は何を感じ、動いていたのだろうか。そしてそれは、普段はできないことなのだろうか。震災のような状況にならないと、できないことなのだろうか。
支援を始める前に受け取っていたバトンがあった
神戸市東灘区に本社を構える白鶴酒造株式会社では、震災の後工場が復旧するまでの間、本社内にある生産現場向けの大浴場を市民に解放していたという。当時の話を管理本部の大利清隆さんに伺った。そして、地元呉田地区の堀口裕司さん、綾田秀子さんにも話を伺うことができた。
大利さんは当時、7歳、5歳、3歳の3人の子どもとともに家族5人で暮らしていた。その日は朝早くからの仕事があったため既に起床しており、朝の支度をするなかあの大地震が起きた。家具が入り乱れるなか、なんとかマンションを出た。
暗闇の中にうっすらと見えたのは、阪神高速が根もとから倒れているあの光景だった。
「これは関西おわったな、、、」
とにかく、目の前の崩れた家々から挟まっているご近所さんを助け出す。「会社も大変なことになっているはず」という想いが脳裏をよぎる。まずは家族を安全な場所に避難させて、自分は会社に向かわなければ。気持ちばかりが焦る。幸いにもその晩、奈良に住む親戚に家族を預かってもらえることになった。
工場にいち早く向かった社員は、タンクの方から濁流のようにザーザーと大量の液体が流れてくるのを発見した。近づくとアルコールの香りがする。「これは酒だ」と分かったが、既に90センチ以上溜まっていて止められるような状況ではない。もう、ただただ立ち尽くすしかなかったという。
大利:私も家族を避難させてから、会社に向かいました。そして復旧作業をしながら、自宅の電気もガスも水道も使えないことを総務部長に相談していたんです。「それなら会社に泊まればいいよ」となりまして。会社の会議室に布団を用意してもらい、泊まらせてもらえることになったんです。会議室には、他にも避難所に入れなかった社員も含めて10名、取引業者の方が10名と計20名ほどが寝泊まりしていました。当時は社長もずっと泊まり込んでいたんですよ。
えっ、社長さんもですか。
大利:もう一つ前の社長もそういう人だったと聞いています。戦後、出兵していた男性たちが大勢神戸にも帰ってきたけれど、そこは焼け野原で仕事もなく、食べ物もなかった。そんな時、当時の社長は自宅を開放して食事を食べさせていたそうなんです。その理由を、こう言っていたそうです。「若い血気盛んな人たちがお腹をすかせて街をうろつくと、絶対に良くないことが起こる。しかし、彼らをお腹いっぱいにしてあげれば。次にしなければいけない事は日本を良くすることだという考えになるだろう。だから家でごはんを食べさせなさい。」と。そうして開放された自宅には、たくさんの人が集まっていたそうです。
自分や自分の家族だけで生きているわけじゃない。地域全体で生きているという感覚だろうか。
毎晩、1日の復旧作業が終わると、社長・総務部長・労働組合委員長・大利さんの4人で「明日は何をするか」を話し合っていた。そのなかで、こんな話が出てきた。
「うちは水は助かっている。使えなくなった井戸もあるが、使える井戸もたくさん残っている。それなら工場が稼働できない今、街の人に会社のお風呂を開放しようじゃないか。」
大変な状況のなか同時に支援も。そこには何があったのでしょうか?
大利:当時は「日常をとり戻す」ということに必死だったように思います。たった一瞬のことで、まるで違う世界にワープしたようでした。それまで命の危険を感じることなんてなかったので、日常のありがたさを、その時初めて実感しましたね。そして、私は支援をする立場でもあったけど、その前にたくさん支援を受けていたんですよ。会社には、復旧に向けて関連する企業の方が大勢ボランティアに来てくれていたんです。会社に言われて来たんでしょうが、一緒に寝泊まりして、夜はお酒を飲みながら色んな話をしました。彼らにはすごく助けてもらいました。
大利さんには、支援を始める前に受け取っていたバトンがあった。
白鶴さんのお風呂を実際に利用したという綾田さん。どうでしたか?
綾田:いやぁ、それはもう良かったですよ。白鶴さんのお風呂は広いしね。帰りには、お酒用の大きな袋に入ったお水も分けてもらったりしてね。本当にありがたかったです。
自治会を通じてお風呂開放のお知らせすると、こうして近所の顔見知りの人たちがたくさん足を運んでくれた。「元気だったんですね。良かったです!」と声をかけあったり「久しぶりにお風呂に入って、気持ちよかったです!」という言葉をもらったり。なかには、今になっても「あの時のお風呂は一生忘れられない」と話してくれる人もいるのだそう。
当時から阪神住吉駅前で「ことぶき」という食堂を営んでいる堀口さん。堀口さんもまた震災のあと「日常を取り戻す」ために毎日動き回っていた一人だという。
堀口:震災の後、店が心配で見に行ったら、近くで炊き出しをやっていてね。そこで、余ってコチコチになったおにぎりをたくさんもらったんです。このままじゃ食べられへんしな、ということでおじやを作ることにしたんですよ。店の前で、一斗缶使って焚火みたいにしてやってたら、寒かったからかな。みんな火に寄って来るもんですね。たくさん集まってきて。それを結局1カ月くらい続けたんですよ。近所のラーメン屋さんとか、市場の人とかが冷蔵庫のものダメになるからと色々と持ってきてくれてね。色んなもの作りましたよ。お好み焼きとか焼きそばとかね。車で「ことぶきの前で炊き出ししてますよ~」ってマイクで案内したりね。あったかいものが食べられないから、みんな並んで来てくれました。
被災した堀口さんのお店に修繕業者がきたのは、半年後のことだそう。自身のお店再開の目星なんか全くたっていない。そんな状況のなか、動こうと思ったきっかけは何だったのだろうか。
堀口:震災後3日間は、北区に住む娘の家に行っていました。北区ってここから山ひとつ越えたところなんですけどね。向こう側は何ともなかったんですよね。そこで3日間は、私もしょんぼりしていたんですよ。それでもまぁ、自宅の片付けに帰ってきて。ふらっと近所のお菓子屋さんに立ち寄ったんです。そしたらお店の人が、こんな時だからこれも持っていき〜、あれも持っていき~って色々くれるんですよね。それをみてたら、ぼくも何かせないかんなあ、逃げてばかりいてはいかんなあと思ってね。
大利さんと堀口さん、同じようなことを言っている。あったかい気持ちのバトンをもらって、次は自分がそのバトンを渡していく。
大利:これは確証があったり、裏付けがある訳ではないのですが、大きな災害のあった年は、どういう訳だか日本酒がたくさん飲まれているんです。これはあくまで私の考えなのですが、大きな災害があると改めて自分のアイデンティティっていうんですかね。本来自分が大事にしていることは何なのかと見直すのでしょうか。
それは、命の危機を感じた親が「自分の子を守らねば」「自分の住処を守らねば」とするような動物的本能なのだろうか?
あぁ、「生きる」ことが身近に在るときの人間って。
なんだかやさしいなあ。