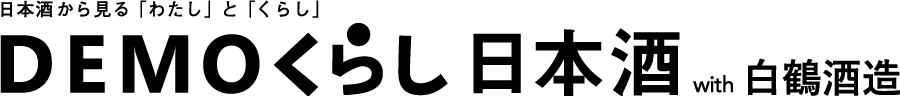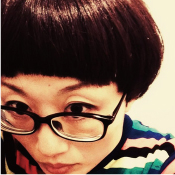文: 桂知秋
日本酒の聖地とも呼ばれる、奈良は御所(ごせ)で創業から300年以上の歴史を持つ油長酒造。柱とするのは古代や中世の奈良酒を甕仕込みで再現したブランド「水端(みづはな)」と、奈良酒の伝統技法と現代の技術を融合させて次世代につながる日本酒を模索するブランド「風の森」。一見真逆にも思える、伝統とテクノロジーという二つのキーワードをどう捉えて酒造りをしているのか。13代目山本長兵衛さんにお話を伺った。

歴史本から紐解く、当時の「最先端技術」。
伝統とテクノロジー。そのキーワードを聞いて山本さんは「こんな本があります」とおもむろに目の前で古い本を開いた。その本の表紙には『多聞院日記』と書いてある。
「興福寺の多聞院にて1500年代頃に書き綴られた日記です。ほらここ、1568年5月の記述に初めて“酒袋”という言葉が出てくるんです。お酒のもろみを入れて搾るための袋ですね。今はみんな当たり前にお酒を搾っていますが、この文献のこの箇所に出てくるまで誰も書いていないんです(※)。おそらくそれまではお酒というのは搾られていないどぶろくが主体だったということでしょう。同じ年の6月には”酒を煮させて樽に入れる”という記述がでてきますが、これはめちゃくちゃ画期的なんです。家で飲むしかできなかったどぶろくを、搾って、火入れして樽に入れることで遠くまで流通させられるようになったわけですから。なぜ寺院でそんなことがおこったのか。戦国時代は朝廷の財源が減り、奈良の大寺院は自分たちで経営資金を賄っていく必要があった。お金を儲けないといけなかったわけです」。
※清酒(すみさけ)という言葉は奈良時代の木簡に見られますが、もろみの上澄みを汲んだものだと考えられています。
山本さんはさらにもう一冊の古い本を開く。江戸時代初期に伊丹の鴻池流の醸造家が書いた「童蒙酒造記(どうもうしゅぞうき)」には、先ほどの多聞院日記にでてくる奈良の酒造りの方法“奈良流”をもとに伊丹や小浜(宝塚)など各地に流派ができていったという記述があった。
「この時代には寺院醸造で起こった技術革新での造り方が当たり前になり、各地でその技術をうまく取り込みながらさらにその時代のエッセンスをまた載せて、日本酒を進化させていった。この本の作者も当時の最先端の技術を記しているだけで、誰も歴史や伝統をつくりたいなんて思っていなかったはず。たまたま今振り返ってみると、技術の積み重ねが歴史や伝統になっているだけ。技術をレイヤーのように積み重ねてきたものが今の日本酒なんです」。


菩提酛と冷却能力の高い発酵タンク。
なぜ甕から木桶に変わったのか。なぜ真夏にお酒を造らなくなったのか。山本さんは次々とこれまでの日本酒の技術の淘汰と進化の道のりを語る。聞けば聞くほど、そこには人間の“欲望”が常につきまとっている気がした。
「そうですね、まさに欲望なのだと思います。もっと美味しいお酒を造りたい、もっとお金を生み出したい、というその欲望のためにその時代ごとの技術が重なっていくわけです。車だって最初は馬より速ければ満足だったのに、今や時速300kmだって出せる。やっぱり人間っていうのは自らのその取り組みをちょっとでも研ぎ澄ませていきたいという欲望があるんじゃないでしょうか。言ってしまえば自分も“お酒をより魅力的な液体にしたい”という欲望でやっているのかもしれない」。
昔の人たちがそうしたように、その欲望のもと山本さんたちも今の日本酒にさらに技術をレイヤーで積み重ねていく。
「我々が目指しているのは、油長酒造にしか造れないお酒。だから奈良でしかできないお酒、そして美味しいお酒をつくるためであれば、我々は古いものも新しいものも融合させて重ねていきます」。
山本さんの父親である先代は、奈良のお酒のアイデンティティを求めて歴史を紐解こうと酒蔵仲間とともに「奈良県 菩提酛による清酒製造研究会」を発足。菩提山正暦寺でかつて造られていたという日本最古の酒母、菩提酛をお寺や奈良県と共に研究し、2年がかりで寺院醸造を復活させたという。以降、正暦寺では20年以上毎年菩提酛造りが行われており、油長酒造も正暦寺でその菩提酛を共同醸造しているそう。
「将来的には風の森の全種類を菩提酛(自社で醸造)に切り替える予定です。ただそれは古いものを使いたい、という単純なことではないです。菩提酛を使うことで奈良の歴史を味わうことにもなりますし、その酒母のみが紡ぎ出せる味わいを重ねることもできる。かと思えば、真夏でも真冬並みの品質がつくれるようなすごい冷却能力の高い発酵タンクみたいなバッキバキの現代的な技術も重ねていっています」。
大甕で仕込む酒造りを始めたわけ。
「ただ、日本酒っていうのはそうやって長い歴史を積み重ねて今があるものですから、新しいことをやろうとした時に、歴史そのものやかつてあったかもしれないレイヤーを知っていないと、次なる新しいレイヤーを生み出す時に自信もわかないし、なによりなんか申し訳ない気がするんです。日本の主食を発酵させて、嗜んで。日本酒は嬉しいときも悲しいときもずっと日本人に寄り添ってきたものなわけですから」。
見せていただいた文献に奈良時代の酒造りが書かれた木簡の写真が載っていた。長い歴史に身を置いているという矜持とその歴史へのリスペクト。それをしっかり土台にしながら新たな技術革新を起こしていこうとしているのだろう。山本さんは、木桶仕込みよりも前の時代に行われていた、大甕で仕込む酒造りも始めた。「水端(みづはな)」と名付けられたそのブランドの説明書きには酒米の種類や精米歩合と一緒にレシピの”参考文献”として「御酒之日記」や「多聞院日記」が記載してある。
「伝統をしっかり伝えていく役割も担っていかなければいけないとは思っています。でも昔にやっていたことがすごいというわけではない。その中で面白い技術を見つけたら風の森に重ねていくようなことをやっていけば面白いんじゃないかと。古いことを掘り下げて、歴史の中で淘汰されたレイヤーを見つけにいく。そんなイメージでやっています」。


「いくらテクノロジーが進化してもオートマチックで酒を造ることはできない」
甕仕込みの酒蔵の隣には、風の森の酒蔵。外見は昔ながらの蔵の佇まいだが、「発酵室」と付けられた扉を開けるとそこには近代的なタンクが並んでいる。


「先ほどの享保蔵とは真逆の世界でしょ。前衛的な環境です。温度も1分ごとに計測されパネルで見ることができます。人間がひとつひとつ温度を測っていたらこれほどの数のデータを集めることはできません。そんなことは機械に任せたらいい。人間はその結果を見て、どういう温度にしたらもっとお酒が美味しくなるんだろうとか、人間にしかできない判断をすることが人間の仕事だと思っています。いくらテクノロジーが進化してもオートマチックで酒を造ることはできない。微生物の営みをうまく動かすのは人間なんです。昔だって発酵をコントロールするために甕に藁をかぶせたりしていたのではないかと思います」。
他にも米を煎ってみたり、搾り機を使わずに特殊な発酵タンクを用いて冷却や圧力をコントロールすることで、もろみの中に上澄みを造ってみたり。新しい技術を常に試しているという山本さん。
「こうやって私たちが今やっていることが30年後は当たり前になっているかもしれないし、100年後にはそのレイヤーは落とされていっていることだってありえます。でもひょっとしたら…。そう思って科学とロマンの狭間でずっと揺れ動きながらこれからもやっていくんだと思います」。